こんにちは。いきいき行政書士事務所です。
今回は、「特定技能2号の対象拡大」について、行政書士の視点から詳しく解説いたします。
人手不足が深刻化するなか、外国人材の活用は中小企業にとって避けて通れないテーマです。今後、どのように制度が変わっていくのか?企業はどのように備えるべきか?
制度の要点と実務上のポイントを、わかりやすくお伝えします。
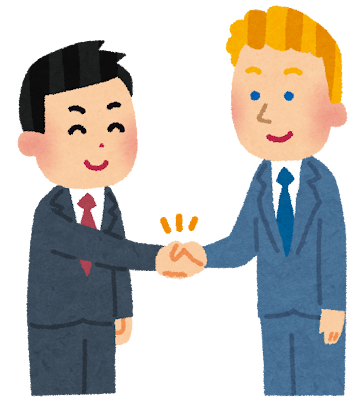
◆ 特定技能制度とは?
まずは制度の基本を簡単におさらいしましょう。
特定技能制度は、2019年にスタートした在留資格の仕組みで、「一定の技能」と「日本語能力」を持つ外国人が、特定の業種で働くことを可能にしています。
現在は以下の2種類の資格があります。
- 特定技能1号:14業種(介護・農業・建設・外食など)で最長5年間の就労が可能。家族の帯同は不可。
- 特定技能2号:現在は建設と造船業のみに限定されているが、無期限の在留と家族の帯同が可能な上位資格。
今回、この2号の対象を介護や外食業などにも拡大する方針が示されました。
◆ 特定技能2号の拡大がもたらす変化
特定技能2号が広がることで、企業にとっては次のようなメリットが見込まれます。
◎ 外国人材の「長期戦力化」
これまでは、せっかく採用・育成した外国人が5年で帰国しなければならず、「本格的に戦力化したころに退職」というケースも多く見られました。
しかし、2号に移行できれば無期限の就労が可能になり、企業としても人材投資の回収がしやすくなります。
◎ 家族帯同による定着率アップ
2号資格では配偶者や子どもの帯同が認められます。
家族と一緒に暮らせることで、生活の安定度が上がり、日本で長く働きたいという意欲につながると期待されています。
◎ 対象業種の拡大がもたらすチャンス
今回の対象拡大では、以下の分野が有力視されています:
- 介護
- 外食
- 農業
- 宿泊
- ビルクリーニング
- 産業機械製造
- 素形材産業(鋳造・鍛造など)
これらは、地方の中小企業や人手不足が特に深刻な業界ばかりです。
制度の拡大により、今まで以上に柔軟な人材確保が可能になるのです。
◆ 制度拡大に伴う注意点と課題
メリットが大きい一方で、注意すべき点や企業側の課題も見えてきます。
【1】特定技能2号は「誰でも取れる資格」ではない
2号へ移行するには、実務経験の蓄積や上位の技能評価試験への合格が必要です。
つまり、企業が「この人に長く働いてもらいたい」と思っても、本人のスキルや日本語力が条件を満たしていなければ、2号への移行はできません。
✅ポイント:技能実習 → 特定技能1号 → 特定技能2号という流れを見据えた人材育成計画が求められます。
【2】企業に求められる支援責任が増す
2号では家族帯同も可能になるため、住居の確保、子どもの学校、病院、地域との関係など、生活全般を支える体制づくりが重要になります。
とくに地方企業の場合、行政サービスが都市部より限られていることもあり、支援機関や行政書士との連携がカギを握ります。
◆ 行政書士ができる支援とは?
外国人材を受け入れる際、企業単独で対応するのは現実的に難しい場面も多くあります。
私たち行政書士は、以下のような支援を行っています。
- 在留資格申請(特定技能1号・2号)の書類作成・代理申請
- 受入機関の届出・適合性確認書の作成支援
- 雇用契約や支援計画の作成アドバイス
- 監理団体や登録支援機関との調整
- 労務管理や外国人とのトラブル予防相談
また、制度変更があるたびに必要書類や手続きも変わるため、最新情報のキャッチアップも重要です。
定期的なアドバイザリー契約を結んでいただくケースも増えています。
◆ 企業が今からできる4つの準備
- 制度の正しい理解
特定技能制度と技能実習制度の違い、2号への移行条件を整理しましょう。 - 自社のニーズ整理
外国人材にどんな業務を担ってほしいのか、現場と連携して明確にしておきます。 - 中長期的な受け入れ体制の見直し
住居支援、生活相談窓口、日本語学習のフォローなど、受け入れに必要な支援体制を洗い出します。 - 専門家との連携体制構築
行政書士、社労士、登録支援機関などとの連携を通じて、スムーズな手続きを整えましょう。
◆ 地方企業の成功事例:ある農業法人のケース
特定技能1号を導入し、成功を収めている地方企業の事例として、ある農業法人を紹介します。
この法人では、季節労働力の確保に悩んでおり、ベトナム人技能実習生を数年受け入れていました。しかし、技能実習は「学ぶ」ことが目的で、5年以内に帰国するため、継続雇用ができない点に課題を感じていました。
そこで、同社は2021年に特定技能1号に切り替えて受け入れを開始。ベトナムからの実習修了者を特定技能1号として採用し、農繁期だけでなく通年雇用ができる体制を整えました。
成功のポイントは以下の通り:
- 支援計画をしっかり整備し、登録支援機関と連携して生活支援体制を整えた
- 就労後も日本語学習や地域イベントへの参加を促進し、定着率を高めた
- 地元の若者との混成チームで業務を進め、多様な働き方を実現
この結果、同社では離職率が低下し、外国人材がリーダー的存在として活躍するようになりました。
◆ 企業側のよくある失敗例と注意点
一方で、制度を正しく理解せずに受け入れを進めてしまった企業では、以下のようなトラブルが生じがちです。
【失敗例1】「言語の壁」を軽視
外国人材が日常会話レベルの日本語を話せるとしても、専門用語や安全管理の説明が伝わらないまま業務を任せてしまうと、事故やミスのリスクが高まります。
→ 対策:マニュアルの多言語化や、社内研修で「やさしい日本語」を取り入れる工夫が有効です。
【失敗例2】文化・生活習慣の違いを理解しない
「遅刻が多い」「指示を出しても動かない」といった声が現場から出ることもありますが、それは指導の仕方や文化の違いによる誤解である場合が多くあります。
→ 対策:外国人材向けの生活オリエンテーションだけでなく、日本人社員への「受け入れ教育」も重要です。
【失敗例3】必要な書類の提出忘れ・期限超過
在留資格の更新や報告義務を忘れてしまい、不法就労の扱いになるリスクもあります。悪意がなくても、法令違反とみなされるおそれがあります。
→ 対策:行政書士や支援機関との契約で、法令遵守体制を外部サポートで補完するのが安全です。
◆ 登録支援機関を使うべきか?判断のポイント
特定技能1号で外国人を受け入れる場合、企業(=受入機関)が自ら「支援計画」を実施するか、「登録支援機関」に委託するかを選択できます。
🔹 登録支援機関を使うべき企業
- 外国人雇用の経験がない、または浅い企業
- 支援内容(生活相談・行政手続き同行など)を自社でまかなえない
- 地方で行政とのやり取りや多言語対応が難しい企業
- 申請書類作成に不安がある中小規模事業者
→ 行政書士と登録支援機関の連携により、申請から就労後のフォローまでワンストップ支援が可能になります。
🔸 自社で支援を行ってもよい企業
- 過去に技能実習や特定技能での受入実績があり、体制が整っている
- 社内に多言語対応可能なスタッフが常駐している
- 日本人と外国人が混成で働く体制がすでに確立されている
→ 自社支援の場合でも、支援計画の実施状況に関する報告義務がある点は変わりません。継続的な法令対応が必要です。
◆ 最後に:外国人材は“使う”ではなく“育てる”時代へ
日本は今、少子高齢化の真っただ中にあります。
今後、外国人材なしでは現場が回らない業種もさらに増えていくでしょう。
特定技能制度の拡大は、こうした現実に対応するための重要なステップです。
制度のチャンスを生かせるかどうかは、企業の準備と理解にかかっています。
いきいき行政書士事務所では、単なる申請代行にとどまらず、
- 制度説明から雇用計画の立案
- 登録支援機関との連携支援
- 実務に沿ったサポート体制の構築
まで、一貫した対応が可能です。
「制度が難しそう」「失敗したくない」とお悩みの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

